ニュースを眺めていてふと目に留まった言葉がありました。「人殺しの訓練」。一瞬、何のことか分からず、読み進めてみると、その発言が飛び出したのは滋賀県議会の場。発言したのは日本共産党の中山和行議員でした。
「人殺しの訓練」という言葉の衝撃
中央と異なる意見を表明すると除名。誰も処分されず
自衛隊=人殺し は共産党の共通認識なのだろう自衛隊訓練は「人殺しの訓練」滋賀県議中山和行
防衛費は「人を殺すための予算」落選した藤野保史
陸自工科学校「殺人練習をする学校」上尾市議平田通子 pic.twitter.com/QmBC5FRcHn— Kame Ron Diaz(San Diego出身) (@kamesan1959) April 18, 2025
滋賀県高島市にある陸上自衛隊・饗庭野演習場で行われた日米合同の実弾射撃訓練に対し、中山議員は「人殺しの訓練」「人殺しのための訓練」と、本会議で発言しました。言葉そのもののインパクトが強烈で、SNSでも賛否が大きく分かれていましたね。
自衛隊の訓練を批判する立場からの表現だとは分かるけれど、現場で汗を流す人たちにとっては、心ない一言と受け取られても仕方がない言葉だったと思います。実際に、自衛隊家族会からは「侮辱にあたる」として抗議文が提出されるに至りました。
自衛隊家族会の怒りと、その背景
家族会の言い分にも、確かに耳を傾ける必要があります。配偶者や親、子どもが自衛隊で任務に就いている立場からすれば、「人殺し」という言葉がどれほど深く刺さるか。任務の中には災害救助や人命救助など、まさに命を守るための活動も数多く含まれています。
一方で、「訓練とは何か?」という問いも浮かび上がってくるわけです。もちろん、自衛隊は軍事組織であり、武器を扱う訓練を行う。それは事実。でもその行為をどう捉えるかによって、表現の重みや立場ががらりと変わってしまうのだと感じました。
共産党県議団の対応と謝罪
問題発言があったのは3月ですが、その後、共産党滋賀県議団は「不適切だった」と謝罪を表明しました。代表の節木三千代氏が、議会運営委員会で謝罪を述べ、有村議長も中山議員に口頭で厳重注意をしたとのことです。
ただ、ここで終わらせるのではなく、この件を通じてもっと根っこにある価値観の違いや、社会における軍事組織の役割への考え方を見つめ直す必要があるように思いました。
政治家の「言葉」はただの意見では済まされない
今回の一件を見ていて一番感じたのは、「発言に責任を持つ」ということの重さです。一般人がSNSで発した言葉でも炎上する時代に、公の場での言葉は何倍もの重さを持つはずです。
「言論の自由」はもちろん大切。でも、自由には責任がついてくる。そのバランスをどう保つのか、政治家に限らず、私たち一人ひとりに突きつけられているテーマなのかもしれません。
自衛隊の「役割」は本当に見えているのか?
これまで私自身、自衛隊について深く考えることはあまりなかったのですが、災害時に被災地で泥にまみれながら活動する姿を見るたび、「ありがたいなあ」と心から思っていました。そういう現実を目にしていると、「人殺し」という言葉にはやっぱり抵抗があります。
もちろん、平和主義の観点から軍事訓練を疑問視する視点も理解はできる。でも、訓練を受ける側には、国家の指示に従って動く責務があるだけで、そこに個人の「殺意」なんてものはないでしょう。そう思うと、発言の切り取り方一つでどれほど多くの人を傷つけるかを改めて考えさせられます。
政治の場に「対話」はあるのか?
今回の発言は、ある意味で「感情的」な響きがあったからこそ問題が大きくなったとも言えそうです。冷静な論拠に基づいた発言であれば、議論の入り口になった可能性もあったのに、ただ感情をぶつける形になってしまったのは、少し残念な印象を受けました。
そして、こうした言葉がひとり歩きしてしまう現代だからこそ、対話を大事にした政治のあり方が求められているのではないでしょうか。
おわりに:この問題から私たちが学ぶべきこと
中山議員の発言に対する怒りや賛否両論を見る中で、ただの「失言騒動」として片付けてしまうには惜しいと感じました。この一件には、言葉の持つ力、表現の自由と責任、自衛隊の存在意義、そして政治家の役割など、考えるべきテーマがぎゅっと詰まっていると思います。
「誰が正しい」「誰が悪い」と単純に言えないからこそ、こうした出来事を通じて、自分自身の考え方にも少し揺らぎが生まれたりする。それがニュースを“読む”ということなのかもしれません。
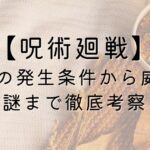





コメント